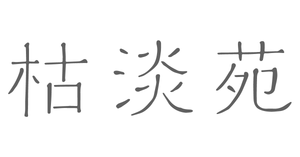「自分のウェブサイトを持つ」 私企業Webサービスの代替としてのインディーウェブ(The IndieWeb Movement)
indeweb.orgより拝借しています
僕は思うのだが、どうもひっかかるのはコンピュータやネットワークそのものではなくて、それらを祭り上げているカルチャーのほうなのだ。(草思社 インターネットはからっぽの洞窟 より)久しぶりのブログ投稿です。ご無沙汰しています。
枯淡苑店主の照井です。
2022年ももう終わりが近づいている中、Twitterの動向が痛ましいほどに荒れていますね。
同社が今後どのような道を辿っていくかは興味ありますが、私個人としてはTwitterをはじめSNSの利用はかなり控えめになっており、仕方なく利用している側面が強いです。
長い間、従来のSNSやブログとは違う形でインターネットを楽しむやり方を模索していました。
その最中、2つほど面白い文化・活動を見つけまして、そのうちの1つが「インディーウェブ」(the IndieWeb Movement)です。
現在進行形のTwitterユーザー流出(出国?)の最中、もしかしたら今後のネット利用に関して多くの人に新たな視点を与えてくれるヒントになるかと思い、本投稿でインディーウェブの概要をご紹介したいと思います。
免責的に書いておくと、インディーウェブはTwitterをはじめとしたSNSを完全に代替するような考え方ではないですし、本投稿で「Twitterの次はインディーウェブだ!」と主張するものでもないです。
そして、紹介する私自身も歴史的背景や技術すべてを把握してるわけではないのでここでの説明に過不足・誤りが幾分含まれることはご容赦ください。ほとんどの情報は、IndieWebを参考にしています。
インディーウェブとは
インディーウェブのコンセプト
インディーウェブは、特定の原則に従って作られた、インデペンデントかつパーソナルなウェブサイトを持つ人々のコミュニティを指します。(別ページの紹介では、"企業サイト"に対する人間中心の代替手段(オルタナティブ)であるともあります)
その原則として代表的なものとしては、以下が挙げられています。
- Owning your domain and using it as your primary identity
- Publishing on your site (Optionally Syndicating Elsewhere)
- Owning your data
粗っぽく意訳します。
- 自分のサイトドメインを持ち、それを基本となるアイデンティティとして取り扱う
- 自分のサイトを公開する(任意で他の場所でも発信する)
- 自分自身のデータを所有する
要は「terui.com」のようなドメイン(ネット上の住所みたいなもの)を取得して自分のサイトを作成・公開する、そしてそのサイトを自宅のように中心として捉えてウェブ活動を行なっていくものと理解しています。
起こりは、2011年ごろに米国オレゴン州はポートランドで行われたIndieWeb Campというイベントから派生した運動らしいです。発起人の中に『カーム・テクノロジー』の著者であるAmber Caseもいたそうな。ただし、それ以前から同様の考え方は生まれていたようです。
そういった活動が起こる背景として、SNS・掲示板などで起こる不毛な議論・交流の窮屈さ、私企業のデータ資本の養分となることへの忌避、短命なWebサービスによるコンテンツ・著作権管理の制限と煩雑さ、幾度となく起こる個人情報流出......ここではあげきれないほど多くの理由があるようですが、黎明期に自由を謳ってきたインターネットの精神と矛盾してきたことも、インディーウェブの概念を取り込んだ人々が生まれる動機にもなっていると思われます。
古き良きインターネッツではないですが、民間企業のSNS・ブログサービスなどをなるべく介さず、ほぼスクラッチでウェブサイトを構築してコツコツ運営していく、やや牧歌的な香りがしますね。
しかしながら、この流れというのは知れば知るほどインターネット老人会への回帰というより、旧来のシンプルな技術を駆使して理念を実現しようとしているきらいがみられるのです。
「自分のサイトを持つ」ということ
このムーブメントにおいて技術的にも理念的にも重要になるポイントが「自分が所有するドメイン」という点です。あまり技術的になりすぎないように書きます。
例えば、多くのWebサービスにおいて会員登録時にIDが割り振られ、あなたは自分のデータ(個人情報を含むテキスト、写真、動画など)を提供しますが、何かの弾みでアカウントを停止されたりすると、自分がコツコツ上げてきたデータを取り戻すのは難しいです。
なぜならそのサービス上のデータは、「運営企業がアクセス制限や規約などで管理している」からです。
その時に自分が所有するドメインの中にデータを持っていれば、半永久的に手元に置いておき、「自ら管理することが可能」になります。
ほかにも、ドメインが一定である限り、あなたがサイト運営に関するツール・サービスを変えたとしても、人々は同じドメインにアクセスすればあなたのサイトを見つけられます。
あなたがコメント欄やメールフォームなど何がしか会話ができるツールを提供していれば、既にアカウント停止をされ追い出されたWebサイト経由でも、友人・知人と継続して交流が可能になるのです。
ややこしいですが、TwitterやInstagramで与えられる住所はドメインではないので、サービス提供者が勝手に住所を変更したり、アカウントを削除したりするとほぼ二度とデータは戻りません。
あくまで例の一つでしかありませんが、こういった企業サイトの運営方法に大きな違和感を感じた旧来のネットユーザーたちが、長期的な自主性を取り戻す現実的な手段として、自らのドメインを所有することがうってつけでした。
参考として、こちらの「Why have your own website」というセクションにいくつか事例があります。(英語ばかりですが、google翻訳などを使えば日本語でも読めます)
なぜ自身のウェブサイトを作るに至ったか、このムーブメントに乗っかることになったのか、長いですけど背景が真摯に語られていると思います。その多くは私も共感できるものが多いです。
IndieWeb Campが薦めている、特にこの2つはおすすめです。
IndieWebCamps create tools for a new Internet.
An Introduction to the IndieWeb
インディーウェブをとりまくキーワード
この運動の考え方をもう少し理解するために、この界隈で使われる重要そうな用語をいくつかピックアップしてみます。
Silo(サイロ)
営利企業による、コンテンツそのものが資本となり、会員登録などアクセス時に制限(壁)があるWebサービス。ほとんどのSNSが当てはまる。
他の特徴として、厳格な規約や、ユーザーが作成したコンテンツの権利・入出力に制限があるなど。
(元の言葉は、家畜の餌を貯蔵する塔などを指しています。イメージは、マトリックスのマシン・シティにある人間栽培施設らしいです)
POSSE
「Publish (on your) Own Site, Syndicate Elsewhere」の略称。本記事のサムネイルやトップで使われている画像は、POSSEの図解。
「最初に自分のサイト(を持って)で公開して、他の場所でも発信する」という意味。他SNSを利用する友人にも投稿を見てもらうため、というのが主となるらしい。
Webコミュニティサービス(Twitter連合、マストドン連合、Facebook連合など無数にある)の利用者は「自分/あなたがどの連合に属しているか」によって交流の幅は制限されてしまうが、あえて「友人とのつながり」を重視してアカウントを保持し、「あなたの状況を知らせる」「(Web上での)友人との交流を続ける」ことを目的とした考え方となっている。
例えばあなたがTwitterを辞めてしまえば、Twitterだけでつながっている友人はsiloの特性である壁によってあなたの投稿を見られなくなるが、自アカウントを残して自サイトの更新内容を投稿して近況を伝えれば、いいねやコメントも含め交流は途絶えなくなる、というわけだ。
逆の概念として、先にサードパーティサービスで公開して自サイトに集約する「Publish Elsewhere, Syndicate (to your) Own Site(PESOS)」がある。
Backfeed
POSSEによって発信された投稿へのリアクションを自サイトの元記事に引いてくる。コメント、いいねなどの集約・長期保持・良質な交流などが目的。
ここがわかりやすい例。「via xxxxxx.com」で経由元がわかる。
New App Engine logo | snarfed.org
やり方としては、Siloのサービス群が持つAPIを使うか、Webmentions* という技術も利用されるそう。
*サイト(ドメイン)間での会話(コメント、いいね、Repostなど)を可能にする技術。トラックバック機能の後継らしい。
他にもOpenID、IndieAuth、Better UI/UX、Use what you make!、”rel=me"、Longevityなど、さまざまなポイントがあるのですが、長くなるのでここでは割愛します。
インディーウェブに対する所感
かいつまんで言ってしまえば、ネット市民としての活動の質を(あくまで主観的にみて)高めていくために自らの情報(サイト)をDIYしていくスピリットとでも解釈できますでしょうか。
私自身、おおむねインディーウェブが抱く課題感や掲げる理想に賛同しますし、一度実践してみたいです。
理想はいろんな意味で高いでしょうが、少なくとも私は、現在の性急で扇情的な流れが溢れるインターネットに関わるより、もっと穏やかでささやかなネチズン活動を営んでいきたいと考えていて、まさにその準備中です。
インディーウェブはもちろん、周辺ジャンルの動きももう少し深掘りして、ある程度のエッセンスと自らがやりたいことを研ぎ澄ましてみたいとも思いました。
全てインディーウェブの考えに従わずとも、一方的なサービス・ポリシー変更も厭わない短命な企業Webサービスに、自分自身の重要な、愛着のある情報を預けることに不安を持つ方にとって「個人で自らのデータを自由に発信・集約・管理できるサイトを持つ」という考え方は一つの選択肢になるかもしれません。
POSSEの考え方をもとにすれば、匿名でやるとしても他サービス(Silo)にあるアカウントとのつながりを消すことなく「自分のサイトを持つ」ことで、より快適なインターネット活動を行えるようになる余地は十分あるのではないでしょうか。
(近い発想で、BufferやIFTTなどを駆使すれば、SNSを直接介さず発信できます。あの忌々しいタイムラインを見なくて済みます)
ただ正直、ネット上で匿名性が好まれがちな日本ではあまり馴染まないと感じました。英語圏の例を見る限り、実名でやられる方が多いのがなぜ多いかの理由は見つかりませんでしたが、なりすまし防止のためにも効果があるのでしょう。
また、技術的な観点から他SNS・ブログサービスのように万人にすぐに利用できる難易度でもなさそうです。けれども、ベーシックな部分をやるだけなら高度なIT技術知識が必要かと言えばそうでもないです。
専門職の方は言わずもがな、ブログやサイトの運営経験があるなら難易度は高くないと思います。まずは自分でドメインを取得するだけです。
インディーウェブの理念に共感する方、ネット生活を豊かにすることに手間をかけられる/かけたい方や、今のネット環境に大きな違和感を持っている方にはマッチする実践方法かもしれません。(大体はTwitter Blue利用料より安く済むのではないでしょうか)
具体的なやり方は、IndieWebCampのほか、ステップを順を追ってわかりやすく教えてくれるサイトもあります。
IndieWebify.Me - a guide to getting you on the IndieWeb
ちなみに、IndieWeb Campのサイト上の情報はパブリックドメイン化しているのですが日本語訳がなく、いずれ翻訳してみたいと思っています。先にどなたかがやってくれるなら大歓迎です。
インディーウェブについてはあまり日本語での情報が見当たらなかったので今回書いてみたのですが、既にWired日本語版でも『デジタル・ミニマリスト』の著者カル・ニューポートが書いてたり、tkskkdさんというプログラマの方が既に実践していました。
私が見つけられてないだけで、実はまだ国内にたくさんのインディーウェブがあるのでしょうか。
というわけで、インディーウェブの活動や日本語翻訳にご興味ある方は色々お話してみましょう。こちらのメールアドレスまでお気軽にご連絡ください。
info@cotan-en.com